
IPO(新規株式公開)は、企業の成長を加速させる強力な手段であり、企業価値向上や信用力増強、資金調達力強化などの多岐にわたるメリットをもたらします。
その一方でIPO準備は長期にわたり、複雑で専門性の高いプロセスを経る必要があります。
ここではIPO準備の流れやスケジュール、各段階における重要ポイント、注意事項などを網羅的に解説します。
IPO成功に向けて本記事を貴社のガイド役として、ぜひ参考にしてください。
IPO準備についての概要

IPO(新規株式公開)とは、未上場企業が証券取引所に株式を上場し、誰でもその会社の株式を売買できる状態にすることです。
IPOは企業にとって資金調達や知名度向上、信用力向上などのメリットをもたらします。一方で上場準備には時間とコストがかかり、上場後も厳しい情報開示義務やコンプライアンス体制の維持が求められます。
IPO準備は長期間にわたるため、各段階における対応事項を事前に理解しておくことが重要です。
※ IPOのメリットに関する詳細は、「中小企業が上場するメリット・デメリットを解説【資金調達】」で取り上げています。
IPO準備におけるスケジュール感
IPO(新規株式公開)の準備は、一般的に上場申請の3~4年前から開始されます。上場申請を行う事業年度をN期とすると、上場までの期間は、N-3期、N-2期、N-1期といった形で表現されます。
IPO準備期(N-3~N-2期)

IPO準備期は上場申請の3~2年前の期間を指し、この期間にIPOに向けた基礎固めを行います。具体的には、次の多岐にわたる準備が必要です。
- 監査法人の選定
- 主幹事証券会社の選定
- 社内管理体制の整備
- 事業計画の策定…など
監査法人の選定
IPOでは、上場申請書類に含まれる財務諸表を監査法人から監査を受ける必要があります。
監査法人は財務諸表の監査だけでなく、内部統制やIPO準備に関する助言・指導も行う重要な役割を担います。
監査法人の選定は、IPO準備の初期段階で行うべき重要事項のひとつです。
監査法人の選定基準としては、以下の点が挙げられます。
監査法人の規模
大手監査法人は豊富な経験と実績があり、信頼性が高い一方で費用が高額になる傾向があります。中小監査法人は費用が比較的安価で、きめ細やかな対応を期待できる一方、IPO支援の実績が少ない場合もあります。
企業の規模やニーズに合わせて、適切な規模の監査法人を選ぶことが重要です。
専門知識
IPOに関する専門知識を有し、経験豊富な監査法人が望ましいです。特に自社の事業内容に精通した監査法人であれば、より的確なアドバイスを受けられます。
実績
過去にどのような企業のIPOを支援してきたのか、実績を確認しましょう。IPO支援の実績が豊富であれば、スムーズな上場準備を期待できます。
監査法人の選定プロセスとしては、以下のようになります。
- 複数の監査法人にアプローチし、資料請求や面談を行う。
- 各監査法人の提案内容や費用などを比較検討する。
- 最終的に、自社のニーズに合った監査法人を決定する。
監査法人の選定は、IPO準備の成否を左右する重要な要素となるため、慎重に進める必要があります。
※ 監査法人の詳細は、「IPOにおける監査法人の役割と選び方|監査法人難民の対策も解説」で取り上げています。
ショートレビュー(予備調査)
ショートレビューとは、IPOを希望する企業が上場に向けての課題を可視化させるために監査法人や公認会計士事務所から受ける調査です。
別名「予備調査」や「短期調査」、「クイックレビュー」とも呼ばれます。ショートレビューを受けることで、企業の現状を把握し、上場までに必要な対応を明確化することができます。
ショートレビューの主な内容は、以下のとおりです。
企業概要・事業内容
会社案内、製品案内、定款、経営計画書、登記簿謄本などを用いて、企業概要や事業内容や強みなどを確認します。
株主構成
株主名簿を用いて、株主構成を確認します。
コーポレートガバナンス体制
役員一覧、株主総会・取締役会議事録、社内規定、組織図などを用いて、コーポレートガバナンス体制を確認します。
会計ルール・ディスクロージャー体制
過去3期分の財務諸表、取引先との契約書、帳票書類、会計処理基準一覧などを用いて、会計ルールやディスクロージャー体制を確認します。
関係会社との関係性
関係会社一覧を用いて、関係会社との関係性を確認します。
会社と役員等の関係性
役員及び主要株主との取引内容を確認します。
ショートレビューは、一般的に上場目標年度からさかのぼって3期以上前に行われます。これは上場申請2期分について、監査法人による監査証明が必要となるためです。
ショートレビューで指摘された課題を改善するためには、社内にIPO準備室を設置したり、プロジェクトチームを結成したりするなどの対応が必要となります。
資本政策の策定
資本政策とは、企業が資金調達や株主構成をどのように行っていくかを決める計画です。IPOにおいては、上場後の安定的な経営基盤を構築するために、適切な資本政策を策定することが重要となります。
資本政策の策定においては、以下の点を考慮する必要があります。
資金調達
IPOでどの程度の資金を調達したいのか、その使途は何かを明確にすることが必要です。資金調達を重視する場合は、持株比率やキャピタルゲインが減少する可能性があります。
持株比率
上場後、オーナー(もしくは経営陣)がどの程度の持株比率を確保したいのかを検討する必要があります。持株比率を重視する場合には、資金調達やキャピタルゲインが減少する可能性があります。
キャピタルゲイン
上場により、創業者を中心とした既存株主がどの程度のキャピタルゲインを得られるのかを考慮する必要があります。キャピタルゲインを重視する場合には、資金調達や持株比率が減少する可能性があります。
ストックオプション
役員・従業員にストックオプションを付与する場合、その割合や条件を検討することが必要です。ストックオプションを付与することで、優秀な人材の確保やモチベーション向上を期待できるでしょう。
相続対策
オーナー家の相続対策として、資産管理会社の設立などを検討する必要があるでしょう。資産管理会社を設立することで、相続税対策や事業承継対策ができます。
投資家からの評価
上場後に投資家から適正な評価を受けられるよう、資本政策を検討する必要があります。投資家からの評価は、株価や資金調達に影響を与えるため重要です。
資本政策は一度決定してしまうと後戻りが難しいため、慎重に検討する必要があります。
主幹事証券会社の選定
主幹事証券会社とは、IPOにおける中心的な役割を担う証券会社です。主幹事証券会社は、上場準備の段階から上場後まで企業をサポートします。
主幹事証券会社の主な役割は、以下のとおりです。
■上場準備のアドバイス
資本政策、社内管理体制の整備、上場申請書類の作成など、IPOに関するあらゆる面でアドバイスを行います。
■証券取引所との折衝
上場申請や上場審査に関する手続きを代行します。
■株式の引受
IPOにおける株式の公募・売出しを引き受けます。
■上場後のIR支援
上場後のIR活動(投資家向け広報活動)を支援します。
主幹事証券会社の選定基準としては、以下の点が挙げられます。
実績
IPO支援の実績が豊富な証券会社ほど、ノウハウが蓄積されており、スムーズな上場準備を期待できます。特に、自社の事業内容に精通した証券会社であれば、より的確なアドバイスを受けることができます。
販売力
IPOにおける株式の販売力が高い証券会社ほど、多くの投資家に株式を販売することができます。販売力が高い証券会社であれば、資金調達を成功させる可能性が高まります。
費用
引受手数料やコンサルティングフィーなど、主幹事証券会社に支払う費用を比較検討する必要があります。費用対効果を考慮して、適切な証券会社を選ぶことが重要です。
支援体制
上場準備から上場後まで、充実したサポート体制を提供してくれる証券会社が望ましいです。支援体制が充実している証券会社であれば、安心してIPO準備を進めることができます。
担当者との相性
主幹事証券会社の担当者との相性も重要な要素です。信頼できる担当者と出会えるかどうかが、IPOの成否を左右すると言っても過言ではありません。
主幹事証券会社の選定プロセスとしては、以下のようになります。
- 複数の証券会社にアプローチし、資料請求や面談を行う。
- 各証券会社の提案内容や費用などを比較検討する。
- 最終的に、自社のニーズに合った証券会社を決定する。
主幹事証券会社の選定は、IPO準備を成功させるための重要な要素となるため、慎重に進める必要があります。
※ 主幹事証券会社に関する詳細は、「【IPOを成功に導く】主幹事証券会社の役割と選び方のポイント」で取り上げています。
内部管理体制の整備
内部管理体制とは、企業が業務を効率的かつ効果的に運営し、財務報告の信頼性を確保するための仕組みです。IPOにおいては、上場企業にふさわしい内部管理体制を整備することが求められます。
内部管理体制の整備においては、以下の点が重要となります。
組織体制
職務権限を明確化し、内部牽制が機能する組織体制を構築する必要があります。内部牽制とは、複数の担当者で業務を分担し、相互にチェックすることで不正やミスを防ぐ仕組みです。
業務プロセス
各業務プロセスを可視化し標準化することで、業務の効率化とミス防止を図る必要があります。業務プロセスを標準化することで、担当者によらず一定の品質で業務を遂行できます。
会計処理
適切な会計処理基準に基づき、正確な会計処理を行う必要があります。会計処理の誤りは財務諸表の信頼性を損なうため、正確な会計処理が求められます。
内部監査
内部監査部門を設置し、内部統制の有効性を評価することが必要です。内部監査部門は独立した立場から内部統制を評価し、改善を促す役割を担います。
リスク管理
リスクを特定し、適切なリスク管理体制を構築する必要があります。リスク管理体制は企業が抱えるリスクを洗い出し、その影響を最小限に抑えるための仕組みです。
情報管理
重要な情報の適切な管理体制を構築する必要があります。情報管理体制は情報漏えいや不正アクセスなどを防ぎ、情報の機密性・完全性・可用性を確保するための仕組みです。
コンプライアンス
法令遵守を徹底するための体制を構築する必要があります。コンプライアンス体制は、法令違反のリスクを最小限に抑え、企業の社会的責任を果たすための仕組みです。
内部管理体制の整備は上場審査の重要な項目となるため、しっかりと対応する必要があります。
事業計画の策定
事業計画とは、企業が将来に向けてどのような事業を行っていくのか、その目標や戦略を具体的に示した計画です。IPOにおいては、事業計画の合理性や実現可能性が審査の対象となります。
事業計画の策定においては、以下の点を考慮する必要があります。
経営理念・ビジョン
企業の経営理念やビジョンを明確にする必要があります。経営理念やビジョンは事業計画の基礎となるものであり、従業員の行動指針となります。
市場分析
PEST分析やファイブフォース分析などを行い、市場環境を分析する必要があります。PEST分析は、次4つの観点から市場環境を分析する手法です。
- 政治
- 経済
- 社会
- 技術
ファイブフォース分析は、業界の競争構造を分析する手法です。
競争優位性
自社の競争優位性を明確にし、それをどのように維持・強化していくのかを検討する必要があります。競争優位性とは他社にない強みであり、企業の収益性を高めるための重要な要素です。
成長戦略
中長期的な成長戦略を策定し、具体的な目標数値を設定する必要があります。成長戦略は、企業が将来に向けてどのように成長していくのかを示した計画です。
リスク管理
リスクを特定し、適切なリスク管理計画を策定する必要があります。リスク管理計画は事業計画に潜むリスクを洗い出し、その影響を最小限に抑えるための計画です。
財務計画
売上高、利益、キャッシュフローなどの財務計画を策定する必要があります。財務計画は事業計画を数値化したものであり、事業の収益性や資金繰りを把握するために重要です。
事業計画は上場審査だけでなく、投資家からの評価にも影響を与える重要な要素となるため、しっかりと策定する必要があります。
関係会社の整理
関係会社とは、上場申請会社と一定の関係を有する会社を指します。IPOにおいては、関係会社の存在理由や取引内容が審査の対象となります。関係会社の整理が必要となるケースとしては、以下の点が挙げられます。
存在理由が不明確
実質的な事業活動を行っていない会社や休眠状態の会社など、存在理由が不明確な関係会社は整理の対象となります。存在理由が不明確な関係会社は、上場審査において問題視される可能性があります。
不適切な取引
上場申請会社と関係会社との間で、不適切な取引が行われている場合は整理の対象となります。不適切な取引は、株主の利益を損なう可能性があるため問題視されます。
経営状況の悪化
関係会社が業績不振に陥っている場合は、上場申請会社の業績に悪影響を及ぼす可能性があるため整理の対象となります。関係会社の業績悪化は、上場審査においてネガティブな要素となる可能性があります。
役員構成
関係会社の役員構成が同族色の強い場合、意思決定の妥当性が疑われるため整理の対象となります。同族会社の場合、経営の透明性や客観性が低いと判断される可能性があります。
管理体制
関係会社の管理体制が不十分な場合、上場申請会社の内部管理体制に悪影響を及ぼす可能性があるため、整理の対象となります。管理体制が不十分な場合、不正やミスが発生するリスクが高まります。
- 関係会社の整理方法
- 関係会社の整理方法は、株式の売却や吸収合併などが考えられます。株式の売却は、関係会社との関係を解消するもっとも簡単な方法です。吸収合併は関係会社を上場申請会社に吸収合併する方法です。
関係会社の整理は上場審査に影響を与える可能性があるため、事前にしっかりと検討する必要があります。
定款変更、社内規程の整備
定款とは、会社の基本的なルールを定めたものであり、社内規程は、会社の業務運営に関する具体的なルールを定めたものです。IPOにおいては、上場企業にふさわしい定款や社内規程を整備することが求められます。
定款変更の主な内容としては、以下の点が挙げられます。
目的
事業目的を明確化し、上場後の事業展開に対応できるように変更する必要があります。事業目的は会社の存在意義を示すものであり、定款に必ず記載することが必要です。
機関
取締役会や監査役会などの機関設計を見直し、コーポレートガバナンスを強化する必要があります。コーポレートガバナンスとは企業統治の仕組みであり、株主や従業員などの様々なステークホルダーの利益を守るための仕組みです。
株式
株式の種類や発行限度額などを変更する必要があります。株式の種類には、普通株式や優先株式などがあります。発行限度額は、会社が発行できる株式の総数を制限するものです。
社内規程の整備においては、以下の点を考慮する必要があります。
法令遵守
各規程が法令に準拠していることを確認する必要があります。法令に違反する規程は無効となるため、法令遵守は必須です。
実態との整合性
規程の内容が会社の業務実態に適合していることを確認する必要があります。業務実態に合わない規程は運用が困難となるため、実態との整合性が重要です。
規程間の整合性
各規程間で矛盾がないことを確認する必要があります。規程間に矛盾があると、従業員が混乱する可能性があります。
運用
規程が実際に運用されていることを確認する必要があります。規程は作成するだけでなく、実際に運用することが重要です。
定款変更や社内規程の整備は、上場審査の重要な項目となるため、しっかりと対応する必要があります。
本格準備期(N-2~N-1期)

本格準備期は上場申請の2~1年前の期間を指し、この期間に上場に向けた準備を本格化させます。
具体的には上場準備監査の実施、内部管理体制の運用確認、上場審査対応準備などを行います。また株式事務代行機関や、証券印刷会社を選定します。
上場準備監査(本調査/詳細調査)
上場準備監査とは、IPO準備企業が上場申請前に監査法人から受ける監査です。上場準備監査では財務諸表の監査だけでなく、内部統制や経営管理体制の評価も行われます。
上場準備監査の目的は、以下のとおりです。
財務諸表の信頼性確保
財務諸表が適切な会計基準に基づいて作成されていることを確認し、投資家に対して信頼性の高い財務情報を提供します。
内部統制の有効性評価
内部統制システムが適切に設計・運用されているかを評価し、財務報告の信頼性を高めます。
※ 内部統制に関する詳細は、「【IPO】株式上場における内部統制の必要性や目的や要素を解説」で取り上げています。
経営管理体制の評価
経営層が効果的な経営戦略を策定し、その実行を適切に管理・監視しているかを評価します。
上場準備監査は上場審査の重要な項目となるため、しっかりと対応する必要があります。
内部管理体制の運用確認
内部管理体制の運用確認とは、本格準備期に整備した内部管理体制が実際に運用されているかを確認することです。運用状況は上場審査の対象となるため、問題があれば改善する必要があります。
内部管理体制の運用確認においては、以下の点を確認します。
■組織体制
職務権限が明確化され、内部牽制が機能しているか。
■業務プロセス
各業務プロセスが標準化され、効率的に運用されているか。
■会計処理
適切な会計処理基準に基づき、正確な会計処理が行われているか。
■内部監査
内部監査部門が有効に機能し、内部統制の評価が行われているか。
■リスク管理
リスク管理体制が構築され、適切に運用されていか。
■情報管理
重要な情報が適切に管理されているか。
■コンプライアンス
法令遵守が徹底されているか。
内部管理体制の運用確認は、上場審査に影響を与える可能性があるため、しっかりと行う必要があります。
上場審査対応準備
上場審査対応準備とは、本格準備期に証券取引所の上場審査に対応するための準備を行うことです。上場審査では、形式基準と実質基準の両方が審査されます。
形式基準とは次の定量的な基準です。
- 株主数
- 流通株式数
- 時価総額…など
実質基準とは、次の内部管理体制などの定性的な基準です。
- 企業の継続性
- 収益性
- 経営の健全性
- コーポレートガバナンス
上場審査対応準備においては、以下の点に注意する必要があります。
形式基準
各市場の形式基準を満たしていることを確認する必要があります。形式基準を満たしていない場合は、上場申請を行うことができません。
実質基準
企業の継続性や収益性、経営の健全性などを証明する必要があります。実質基準は、企業が上場企業としてふさわしいかどうかを判断するための基準です。
上場申請書類
上場申請書類を正確かつ漏れなく作成する必要があります。上場申請書類は企業の情報を網羅的に記載した書類であり、上場審査の重要な資料となります。
ヒアリング
証券取引所からのヒアリングに備え、想定される質問への回答を準備する必要があります。ヒアリングでは、上場申請書類の内容について証券取引所から質問されます。
上場審査対応準備は、上場審査の成否を左右する重要な要素となるため、しっかりと行う必要があります。
※ IPO審査に関する詳細は、「【IPO】上場審査とは?審査基準・流れ・対策ポイントを徹底解説」で取り上げています。
株式事務代行機関の選定
株式事務代行機関とは、株式会社に代わって株主名簿の作成や管理、株主総会に関する事務などを行う機関です。IPOにおいては、上場企業にふさわしい株式事務代行機関を選定することが求められます。
株式事務代行機関の選定基準としては、以下の点が挙げられます。
信頼性
信託銀行や証券代行会社など、信頼性の高い機関を選ぶ必要があります。信頼性の低い機関を選んでしまうと、株主の利益を損なう可能性があります。
費用
株式事務代行機関に支払う費用を比較検討する必要があります。費用対効果を考慮して、適切な機関を選ぶことが重要です。
支援体制
上場準備から上場後まで、充実したサポート体制を提供してくれる機関が望ましいです。支援体制が充実している機関であれば、安心して株式事務を任せられます。
株式事務代行機関の選定は、上場後の株式事務を円滑に行うために重要です。
主幹事証券会社による引受審査
引受審査とは、IPOを担う主幹事証券会社が、企業が上場にふさわしいかどうかを審査することです。
引受審査では次のことが審査されます。
- 財務状況
- 事業内容
- 将来性
- 経営陣の資質…など
引受審査の基準は証券取引所の上場審査基準とは異なりますが、引受審査を通過しなければ上場申請を行うことができません。
主幹事証券会社は上場の直後に企業に問題が発覚した場合、引受審査の責任を問われる可能性があるため、厳格な審査を行います。
引受審査においては、以下の点に注意する必要があります。
財務状況
健全な財務状況であることを証明する必要があります。財務状況が悪化している場合は、上場審査において問題視される可能性があります。
事業内容
将来性のある事業内容であることをアピールする必要があります。将来性がない事業は、投資家からの評価が低くなる可能性があります。
経営体制
適切なコーポレートガバナンス体制を構築していることを示す必要があります。コーポレートガバナンス体制が不十分な場合は、経営の透明性や客観性が低いと判断される可能性があります。
内部管理体制
有効な内部管理体制を整備していることを示す必要があります。内部管理体制が不十分な場合は、不正やミスが発生するリスクが高まります。
情報開示
適切な情報開示体制を整備していることを示す必要があります。情報開示体制が不十分な場合は、投資家からの信頼を得ることが難しくなります。
引受審査は上場審査の前段階として重要な審査となるため、しっかりと対応する必要があります。
申請期(N期)

申請期は上場申請を行う事業年度を指し、この期間に証券取引所への上場申請、上場審査、上場承認取得を行います。
証券取引所への上場申請
証券取引所への上場申請とは、企業が証券取引所に株式を上場することを申請することです。上場申請には、上場申請書類一式を証券取引所に提出する必要があります。
上場申請書類の主なものは、以下のとおりです。
新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)
企業情報や財務情報、ガバナンス情報などを記載した書類です。Ⅰの部は、上場承認後に投資家に対して公開されます。
新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅱの部)
事業内容や経営戦略、リスク情報などを詳細に記載した書類です。Ⅱの部は、プライム市場とスタンダード市場に上場申請する場合に提出が必要です。
グロース市場に上場申請する場合は、「新規上場申請者に係る各種説明資料」を提出します。
※ スタンダード市場に関する詳細は、「東証スタンダードの上場基準をわかりやすく解説|必要書類や注意点」で取り上げています。
※ グロース市場に関する詳細は、「東証グロース上場基準満たして成長を加速【資金調達の最適解】」で取り上げています。
有価証券新規上場申請書
上場申請に関する基本情報を記載した書類です。
上場申請書類の作成は時間と労力を要するため、事前に計画的に進める必要があります。
上場審査の実施
上場審査とは証券取引所が、上場申請を行った企業が上場基準に適合しているかどうかを審査することです。上場審査では形式基準と実質基準の両方が審査されます。
上場審査のプロセスは、以下のとおりです。
1書面審査
提出された上場申請書類に基づき、形式基準への適合性を審査します。
2ヒアリング
上場申請書類の内容について、証券取引所から企業に対してヒアリングを行います。ヒアリングは複数回行われることもあり、質問数は数百にものぼることもあります。
3実地調査
必要に応じて証券取引所が企業の事業所などを訪問し、実地調査を行います。実地調査では資産の実在性や、業務の適切性などが確認されます。
4面談
証券取引所が次の人物と面談を行います。
- 企業の経営者
- 監査役
- 会計監査人…など
面談では、経営者の資質や上場に対する意識などが確認されます。
5上場承認
上場審査の結果、上場基準に適合していると判断された場合、上場承認が得られます。
上場審査は厳格な審査となるため、しっかりと対応する必要があります。
上場承認取得
上場承認取得とは証券取引所の上場審査に通過し、株式を上場することが承認されることです。上場承認後、株式の公募・売出しを行い、上場日を迎えます。
上場承認取得までの流れは、以下のとおりです。
- 上場審査:証券取引所による上場審査を受けます。
- 上場承認:上場審査に通過すると、上場承認が得られます。
- 上場:上場承認後、株式を証券取引所に上場します。
上場承認取得は、IPOにおける大きな節目となります。
上場直前(承認後~上場日)
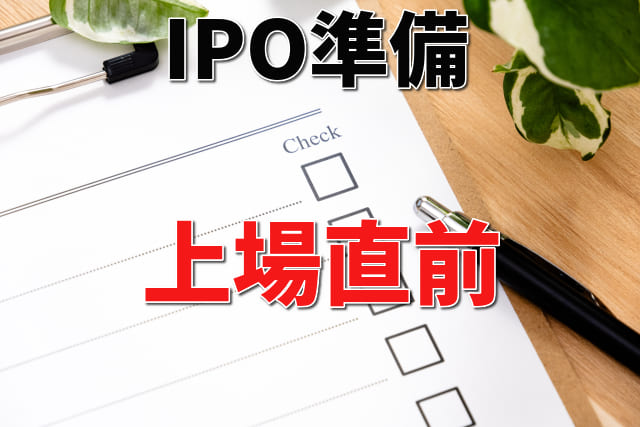
上場直前は上場承認後から上場日までの期間を指し、この期間にロードショー、ブックビルディング、公募・売出し、上場を行います。
ロードショー
ロードショーとはIPOを行う企業が、機関投資家に対して自社の事業内容や将来性などを説明するプレゼンテーションのことです。ロードショーは、機関投資家にIPO株を購入してもらうために重要なマーケティング活動です。
ロードショーの目的は、以下のとおりです。
機関投資家へのアピール
自社の魅力をアピールし、IPO株への投資を促します。機関投資家とは、生命保険会社や投資信託会社など、多額の資金を運用する投資家のことです。
意見交換
機関投資家から意見を聞き、IPO株の価格設定や条件設定の参考にします。機関投資家は、株式市場の専門家であり、企業の価値を評価する上で重要な意見を持っています。
- ロードショーの実施時期と方法
- ロードショーは通常、上場承認後からブックビルディングまでの期間に行われます。ロードショーでは企業の経営陣が、機関投資家を訪問したり、オンライン会議でプレゼンテーションを行ったりします。
ロードショーの資料として、ロードショーマテリアルと呼ばれる資料を作成します。ロードショーマテリアルには、次の内容が記載されます。
- 企業概要
- 事業内容
- 財務状況
- 成長戦略…など
ロードショーマテリアルの作成にあたっては、金融商品取引法の規定に準拠する必要があります。
ブックビルディング
ブックビルディングとは、IPO株の需要予測を目的として機関投資家から購入希望の株数と価格を聞き取るプロセスです。ブックビルディングの結果を参考に、IPO株の公開価格が決定されます。
ブックビルディングのプロセスは、以下のとおりです。
1仮条件の提示
主幹事証券会社が、IPO株の仮条件(価格帯)を提示します。仮条件は、過去の業績や同業他社の株価などを参考に決定されます。
2需要申告
機関投資家が、仮条件の範囲内で、購入希望の株数と価格を申告します。需要申告は、投資家の需要を把握するためのものです。
3公開価格の決定
需要申告の結果を参考に、主幹事証券会社がIPO株の公開価格を決定します。公開価格はIPO株の販売価格です。
ブックビルディングは、IPO株の価格を適正に決定するために重要なプロセスです。
公募・売出し
公募とは企業が新たに株式を発行し、投資家に売り出すことです。売出しとは既存の株主が、保有する株式を投資家に売り出すことです。IPOでは公募と売出しを組み合わせるケースが多く、資金調達と株式の流動性確保を同時に行うことができます。
公募・売出しのプロセスは、以下のとおりです。
1公開価格の決定
ブックビルディングの結果を参考に、主幹事証券会社がIPO株の公開価格を決定します。
2購入申込
投資家が証券会社を通じて、IPO株の購入申込を行います。
3抽選
購入申込が募集株数を超えた場合、抽選が行われます。
4払込
当選者は、証券会社にIPO株の購入代金を払込みます。
5上場
上場日に、IPO株が証券取引所に上場されます。
公募・売出しは、IPOにおける資金調達と株式の流動性確保のための重要なプロセスです。
上場(株式公開)
上場とはIPO株が証券取引所に上場され、投資家が自由に売買できるようになることです。上場日は企業にとって、新たなスタートとなります。上場までの流れは、以下のとおりです。
- 上場承認:証券取引所から上場承認を取得します。
- 公募・売出し:株式の公募・売出しを行います。
- 上場:上場日に、IPO株が証券取引所に上場されます。
上場後は、企業は情報開示義務やコンプライアンス体制の維持など、上場企業としての責任を果たす必要があります。
初値形成
初値形成とは上場日に、IPO株の最初の取引価格(初値)が決定されることです。初値は需給バランスによって決定されます。
初値形成に影響を与える要因としては、以下の点が挙げられます。
- 企業の業績:企業の業績が良いほど、初値は高くなる傾向です。
- 市場環境:株式市場全体の動向が、初値に影響を与えます。
- 公開価格:公開価格が割安であれば、初値は高くなる傾向です。
- 投資家の期待:投資家の期待が高いほど、初値は高くなる傾向です。
初値は、IPO後の株価の動向を占う上で重要な指標となります。
上場後

上場後は、企業は情報開示義務やコンプライアンス体制の維持など、上場企業としての責任を果たす必要があります。
適時開示、法定開示対応
適時開示とは上場企業が投資家の投資判断に、影響を与える重要な情報が発生した場合に、速やかに開示することです。法定開示とは、金融商品取引法や会社法などの法律で定められた情報を開示することです。
上場企業は、適時開示と法定開示の両方に対応する必要があります。適時開示制度とは、取引所の規則に基づき、投資者の投資判断に重要な影響を与える事項について開示を行う制度です。
金融商品取引法に基づく法定開示制度としては、有価証券届出書、有価証券報告書等があります。適時開示制度は報道機関を通じた発表など、投資者にとってより身近な媒体を通じて、迅速かつ公平な会社情報の開示を行う制度です。
ロックアップ管理
ロックアップとはIPOの際に、既存の株主が一定期間、株式を売却できないようにする制度です。
ロックアップは上場直後の株価の安定を図るために設けられています。ロックアップ期間は一般的に90日~180日です。ロックアップ期間中は、既存の株主は株式を売却することができません。
- 2種類のロックアップ
- ロックアップには、「制度ロックアップ」と「任意ロックアップ」の2種類があります。
制度ロックアップとは証券取引所の規則に基づき、IPO前の大株主や第三者割当を受けた株主が、上場後6カ月または1年間、株式の売却を制限される制度です。
任意ロックアップとは主幹事証券会社との任意契約で、大株主や役員・従業員などが一定期間株式を売却できないようにする制度です。
IR活動
IR活動とは、企業が投資家向けに行う広報活動のことです。IR活動は、投資家に企業の情報を正しく理解してもらい、投資判断を支援することを目的としています。上場企業はIR活動を通じて、投資家との良好な関係を構築する必要があります。
IR活動の質の向上には次のことが重要です。
- IPO準備を通して自社の事業理解を深めること。
- マーケットのプロの目線を学ぶこと。
- 投資家との対話を重ね、相互理解を深めること。
資金使途の実行と報告
資金使途の実行と報告とはIPOで調達した資金を、目論見書に記載した使途どおりに実行し、その結果を投資家に報告することです。
資金使途の実行状況は、投資家からの信頼を得るために重要です。上場企業は、資金使途の実行状況を定期的に報告する必要があります。
上場後のフォローアップ|継続的な成長のために

IPOはゴールではなくスタートです。上場後も企業は継続的な成長を目指し、様々な課題に対応していく必要があります。
情報開示義務|適時開示と法定開示
上場企業には、金融商品取引法や会社法などの法律で定められた情報を開示する義務があります。情報開示義務には、適時開示と法定開示があります。
適時開示とは投資家の投資判断に、影響を与える重要な情報が発生した場合に、速やかに開示することです。法定開示とは法律で定められた情報を開示することです。
上場企業はこれらの情報開示義務を遵守し、透明性の高い経営を行う必要があります。
株価変動|市場の評価と業績
上場企業の株価は市場の評価によって変動します。企業の業績や将来性、市場環境などが株価に影響を与えます。
上場企業はIR活動などを通じて、投資家に企業の情報を正しく理解してもらい、適正な株価形成を促す必要があります。
IPO成功のためのポイント|確実な準備と情報開示

IPOを成功させるためには、確実な準備と適切な情報開示が重要です。
早期準備の重要性
IPO準備は、長期間にわたる複雑なプロセスです。早期に準備を開始することで、余裕を持って課題に対応することができます。また、早期に専門家チームを結成することで、専門的な知識やノウハウを活用することができます。
信頼できる専門家チーム
IPO準備には、監査法人、主幹事証券会社、弁護士、税理士など、様々な専門家の協力が必要です。信頼できる専門家チームを結成することで、スムーズな上場準備を進められます。
強固な内部管理体制
上場企業には、法令遵守や株主の利益保護など、高いレベルの内部管理体制が求められます。IPO準備の段階から、強固な内部管理体制を構築しておくことが重要です。
魅力的な成長ストーリー
投資家は、将来性のある企業に投資したいと考えています。IPO準備企業は、自社の魅力的な成長ストーリーを投資家にアピールする必要があります。
適切な情報開示|上場準備の口外に関する注意点
上場準備の情報は、証券取引所が承認するまでは、外部に口外することができません。情報漏えいは、インサイダー取引などの問題に発展する可能性があるため、注意が必要です。
上場準備の失敗を防ぐには
上場準備の失敗を防ぐためには、以下の点に注意する必要があります。
■計画性
IPO準備は長期間にわたる複雑なプロセスです。計画的に準備を進めることが重要です。
■情報収集
IPOに関する最新の情報や規制などを収集し、常に最新の状態を把握しておくことが重要です。
■専門家との連携
監査法人や主幹事証券会社などの専門家と連携し、適切なアドバイスを受けることが重要です。
■社内体制
IPO準備に対応できる社内体制を構築することが重要です。
■リスク管理
IPO準備には様々なリスクが伴います。リスクを特定し、適切な対策を講じておくことが重要です。
IPOの流れに関するよくある質問(FAQ)

Q.IPOにかかる費用はどれくらいですか?
IPOにかかる費用は、企業規模や上場する市場によって異なりますが、一般的に数億円程度といわれています。主な費用項目としては、次の費用があります。
- 監査法人への監査費用
- 主幹事証券会社への引受手数料
- 証券取引所への上場審査料…など
※ IPOの費用に関する詳細は、「上場(IPO)にかかる費用を解説|審査費用、新規・年間上場料」で取り上げています。
Q.IPOの審査で落ちることはありますか?
はい、あります。IPOの審査は厳格であり、審査基準を満たしていない場合は上場承認が得られません。審査で落ちる主な原因としては、業績の悪化や内部管理体制の不備、法令違反などが挙げられます。
※ IPO審査に関する詳細は、「【IPO】上場審査とは?審査基準・流れ・対策ポイントを徹底解説」で取り上げています。
Q.IPOの準備期間はどれくらいですか?
IPOの準備期間は企業規模や業態、社内管理体制の整備状況によりますが少なくとも3年は必要です。これは上場申請2期分について監査法人による監査証明が必要となるためです。
Q.どの証券取引所に上場するのが良いですか?
どの証券取引所に上場するのが良いかは、企業の規模や業種や経営戦略などによって異なります。
東京証券取引所には次の3つの市場があり、それぞれに異なる特徴があります。
- プライム市場
- スタンダード市場
- グロース市場
企業のニーズに合った市場を選ぶことが重要です。
※ 東京証券取引所の3市場に関する詳細は、「東証|プライム・スタンダード・グロースの違いと最適なIPO市場選び」で取り上げています。
Q.中小企業でもIPOは可能ですか?
はい、可能です。中小企業でも上場審査基準を満たしていれば、IPOすることができます。ただし中小企業の場合は大企業に比べて、経営資源や人材が限られている場合が多いため、IPO準備には工夫が必要です。
Q.IPO準備は激務ですか?
はい、一般的にIPO準備は激務といわれています。IPO準備には多岐にわたる業務があり、短期間で多くのタスクをこなす必要があります。また上場審査対応など、プレッシャーのかかる業務も多いです。
Q.上場準備に失敗するケースはありますか?
はい、あります。上場準備に失敗するケースとしては、以下の点が挙げられます。
準備不足
IPO準備には多岐にわたる業務があり、時間と労力を要します。準備不足は、上場審査の不合格や上場後のトラブルに繋がることがあります。
内部体制の不備
IPO準備には社内体制の整備が重要です。内部体制が不備な場合は、情報共有や意思決定がスムーズに行われず、IPO準備が遅延したり、失敗したりすることがあります。
専門家との連携不足
IPO準備には監査法人や主幹事証券会社など、専門家との連携が不可欠です。専門家との連携が不足すると、適切なアドバイスやサポートを受けられず、IPO準備が難航することがあります。
市場環境の変化
IPO準備期間中に市場環境が変化することがあります。市況の悪化や競合の出現などにより、IPOが困難になることがあります。
Q.上場準備の情報は口外して良いですか?
上場準備の情報は証券取引所が承認するまでは、外部に口外することができません。情報漏えいは、インサイダー取引などの問題に発展する可能性があるため、注意が必要です。
Q.N-2期とは何ですか?
N-2期とは、上場申請を行う事業年度(N期)の2年前の事業年度を指します。IPO準備は一般的に、上場申請の3~4年前から開始されます。
上場申請を行う事業年度をN期とすると、上場までの期間は、N-3期、N-2期、N-1期といった形で表現されます。
IPO準備の全体像|成功への確かなステップ

IPO準備の初期段階から上場当日、そして上場後の継続的な成長まで、一連の流れを解説しました。
次の各段階における重要なポイントを、ご確認いただけたかと存じます。
- 監査法人の選定
- 主幹事証券会社の選定
- 内部管理体制の構築
- 事業計画の策定
- 上場審査への対応…など
IPO準備は複雑かつ長期にわたるプロセスですが、本記事が皆様の準備活動を円滑に進めるための一助となれば幸いです。